日本初!「バイオセンサ」のビジネスアイデア&技術力で競う大学生コンペ「BioInnoSense2025」開催レポート

AI・次世代通信・自動運転......。社会のかたちを変える新技術がつぎつぎと現れるなか、近年注目を集めているもののひとつにあるのが、「バイオセンサ」です。生体反応をセンシングするこの技術は、未来の医療や健康管理、さらには環境モニタリングや食品安全の分野などでも活用される可能性を秘めています。
そしてこのたび、そんなバイオセンサを扱った日本初のコンペティション「BioInnoSense2025」が開催されました。本記事では、同イベントの趣旨や概要などをご紹介します。
目次
4つの大学生チームがビジネスアイデアと技術力を競うコンペ
「BioInnoSense2025」は、バイオセンサをテーマとした大学生対象のコンペティションです。タイトルはバイオセンシング(bio-sensing)と、イノベーション(innovation)を組み合わせた造語で、ロゴはバイオセンサにより観測できる電気信号の波形がモチーフになっています。
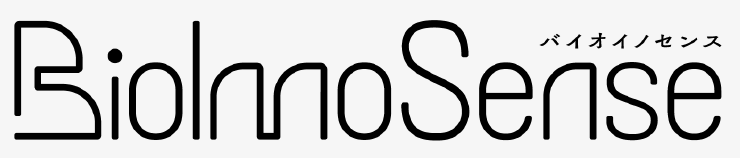
主催を務めたのは、芝浦工業大学(當麻研究室)・東京大学(坂田研究室)・東京科学大学(早水研究室)・早稲田大学(三宅研究室)・マクニカの5者からなる、BioInnoSense実行委員会。そして、同委員会に所属する4つの大学の研究室がそれぞれで最大15名のチームを結成し、コンペティションに臨みました。
「BioInnoSense2025」のテーマは、「バイオセンサの製作とセンシングを通して、日本の未来に資するようなビジネスアイデアを募集すること」です。全体の期間は4ヶ月ほどで、5月初旬のオリエンテーションに始まり、その後は複数回にわたるバイオセンサ講義やビジネスアイデア講義、大学生たちによる中間発表などを経て、8月末に最終発表および審査・表彰の場が設けられました。
審査員を務めたのは、下記の6名です。

また、表彰は下記2つの観点でおこなわれました。
①ビジネスアワード
社会にインパクトを与えられるインスピレーションを持ったビジネスアイデアかどうかを審査し、最も優れたチームに授与。
②テクニカルアワード
開発したバイオセンサの機能性(測定精度、速度、必要なサンプル量)と技術的な新規性、およびチームが開発プロセスにどのように取り組んだかを審査し、最も優れたチームに授与。
以降は、8月31日(日)最終発表当日の内容をダイジェスト形式でお届けします。なお、当日は午前にビジネスアイデアプレゼン、午後にテクニカルプレゼンがおこなわれました。
賑やかな雰囲気の会場
「BioInnoSense2025」の最終発表は、新横浜にあるマクニカのAoT研修センターでおこなわれました。当日は主役である大学生をはじめ、研究室の教授や来賓の方々なども一同に介し、大変な賑わいに。最終発表という厳かな場ゆえに「緊張で押しつぶされそう」という参加者の声もありましたが、約4ヶ月にわたる関係者同士の付き合いもあってか、総じて和やかなムードに包まれていました。
▲会場の様子。
最終発表の冒頭では、東京科学大学の准教授である早水氏が挨拶をおこないました。
「オランダなどでは10年近くも実施されているバイオセンサの大会ですが、その世界大会に日本のチームがひとつも出場していないことを知り、いろいろな人に向けて自分の想いを熱く語っていた」と早水氏。そして2024年、そこに「ぜひやりましょう」と手を挙げたのがマクニカで、日本では初となるバイオセンサのコンペティション「BioInnoSense2025」が実現したそうです。
「日本での大会経験を経たチームがやがて世界に飛び出し、1位に輝く。それはワールドカップに出場するサッカー日本代表チームを作るようなイメージであり、今回集まった皆さんはその精鋭として、熱意をもって頑張ってきてくれました」と早水氏は続けます。
その後もユーモラスな語りで会場をときおり笑いに包みながら、「今回のイベントは日本初であり、こうしてプロの審査員の方々が集まってくださったのもすごいことです。皆さんがやってきたことを、全力で出し切っていただければなと思います」と締めくくりました。
ビジネスプレゼンの部
ビジネスプレゼンおける各大学(研究室)のおもな発表内容は、下表の通りでした。それぞれ「バイオセンサ」という共通のテーマを扱いながらも、その応用分野が多岐にわたることが分かります。
| 大学 | おもな発表内容 |
| ①東京科学大学 | 迅速アレルギー関連感知センサー |
| ②早稲田大学 | 眼球追跡機能を備えた磁性コンタクトレンズ |
| ③芝浦工業大学 | 土壌評価バイオセンサ |
| ④東京大学 | FET型pHセンサによるカビ由来空気質の可視化 |
チームによって発表内容の流れに若干の差異はありましたが、基本的には何らかの社会課題や背景を起点とし、自分たちが提供するサービスやソリューションの詳細のほか、競合比較分析やコスト感なども含めたビジネスモデルなどを解説し、今後の展望で締めくくる......という構成でした。
1チームの発表時間は15分で、さらに各チームとも発表後に審査員との質疑応答の時間が10分設けられていました。審査員からは「市場をさらに深読みしたり、特許戦略をもっとしっかり考えたりすべき」といった高度な指摘もあったものの、発表者の皆さんは懸命に回答していました。
▲なかには、自分たちで建て付けた架空企業の描くロードマップやエコシステムをかなり詳細に発表したチームも。大学生が対象のコンペティションで、ここまでやるのはなかなか珍しいのではないでしょうか。
▲東京科学大学チームの提案する「アレミル」は患者の見た目に関係なく、アレルギー反応をリアルタイムで定量的に教えてくれます。血液ではなく唾液を使うため、注射に抵抗感を抱きがちで、なおかつアレルギー患者に多い子どもに対しても有効にはたらく強みがあります。
▲早稲田大学のチームは、バイオセンサを活用したコンタクトレンズを提案。この製品は磁気によるアイトラッキングを可能とし、眼球運動を日常的にデータ化して蓄積することで、ユーザーのQOL向上(ヘルスケア)や医療機器としての応用、ARやVRといった既存アイトラッキングの代用などに活用できるようです。
▲芝浦工業大学は、土壌に含まれる特定成分の測定ができるバイオセンサを開発。その背景として「園芸をおこなう人が減少している」ことを挙げ、人が園芸を続ける理由や悩みなどに触れつつ、園芸に関する市場調査結果も発表しました。
▲環境によっては、人間の健康に甚大な被害をもたらすこともある「カビ胞子」に着目した東京大学。その成長過程をリアルタイムで観測し、繁殖・胞子の放出タイミングの警告などをおこなう「Sporythm」を開発しました。空気清浄機、エアコン、加湿器といった製品に搭載し、ユーザーの健康志向・安心感・利便性などを高める狙いがあります。
テクニカルプレゼンの部
後半のテクニカルプレゼンでは、各チームとも前半で発表したテーマの技術的な部分について、より詳しい解説をおこないました。おもな内容としては開発した製品の仕組み・それらを使った実験の結果・考察・展望などです。
▲発表内容の一例。内容を理解するには、相応の専門知識が必要です。
▲東京大学はカビ胞子成長過程のリアルタイム観測や、段階的な状況把握を可能とするシステムを提案していました。
▲園芸を好む人々の課題解決を図る芝浦工業大学は、「スマートフォンを使うことで、誰でも肥料を与える適切なタイミングを判断できる」ことをバイオセンサの利点と考えて実験。さまざまな濃度の溶液や肥料水、土壌などを使い、今後の社会実装を目指す際に必要な要件を導きだしました。
▲チームメンバーの大半が外国籍の方で構成されていた早稲田大学。テクニカル部門ではすべて英語によるスピーチで、開発したコンタクトレンズにおける独創性や、素材による違い、アルゴリズムの詳細などが解説されました。
▲食物アレルギーの迅速な発見を目指す東京科学大学は、アレルギー症状の原因物質である「ヒスタミン」と、「トリプターゼ」という酵素の2種類を測定。そのほか、「アレミル」における回路図やスペック、マイコンの処理方法などを明らかにしました。
審査結果発表 受賞チームは?
すべての発表が終わり、会場では懇親会と審査員による審査が並行しておこなわれました。そして審査の結果、ビジネスアイデアの部は早稲田大学、テクニカルの部は東京科学大学が受賞しました(表彰はテクニカルの部を先に実施)。
▲審査員の太田氏から、東京科学大学のチームメンバーにトロフィーが授与されました。
「レポートをはじめとするさまざまな観点で審査をした結果、まだ改善点もあるものの、トータルとしてよくできていると判断しました。今後も先生方にいろいろお聞きしながら、ぜひ次のステップに進んでほしいと思います。本当におめでとうございます」と、太田氏。
続いて、「自分たちのチームは人数が多く、短い期間でチームとして動くのが難しかったですが、1人ひとりがちゃんと動いてくれました。結果を出すことができ、非常に嬉しく思います。今後もさまざまな展望がありますが、自分のやりたいことも含めて進めていきたいです。ありがとうございました」と東京科学大学の代表者がコメント。
▲早稲田大学のチームには、マクニカのSeu(スー)がトロフィーを授与。
続いて、早稲田大学の表彰へ。トロフィー授与を担ったマクニカのSeuは、「どのアイデアも開発中ということもあり、ビジネスアイデアの部は拮抗していました。ただ、そのなかでもプレゼンテーションや質疑応答の完成度が高いと感じたのが、早稲田大学でした。ほかの大学の皆さんも、今後大学やマクニカから支援できることがあると思いますので、またお話させてください」と述べました。
これに対して早稲田大学の代表者は、「今日ほかの大学のプレゼンテーションを聞いて、これは負けたなと思いながら過ごしていたのですが、受賞できて本当に嬉しいです。4ヶ月、このチームで一緒にやってこられて本当によかったなと思っています。主催いただいたマクニカ様と、審査していただいた皆さまにも感謝を申し上げます。ありがとうございました」と返答。
その後も審査員各位からは「今日はすごく勉強させてもらいました」「審査員になれて大変ありがたく思っております」、また主催側の大学(研究室)の先生方からも「中間発表に比べて完成度が非常に高くなっていて、感動しました」「現状を知って成長する、いい方向へ変化していってもらえることを期待して、今後頑張ってほしいなと思います」といったコメントが寄せられました。
さらにイベント視察に来ていたマクニカ社長の原も、「皆さんのワクワクや驚きを世の中に伝える妄想力と、日々の研究で生み出されたテクノロジーの掛け合わせが、新たなイノベーションを生むと思っています。私たちも、今後も皆さんといろいろな共創をさせていただきたいです」と述べました。
おわりに
約4ヶ月にわたる熱戦の末、その幕を閉じた「BioInnoSense2025」。本イベントを通じ、次世代を担う若い人材の可能性を強く実感するとともに、バイオセンサ分野における新しい応用の道筋が見えてきました。私たちは、こうした取り組みが将来の社会課題解決や、新産業の創出につながることを大いに期待しています。
「BioInnoSense」は、今後もさまざまな企業様との連携を深めながら継続開催を予定しております。本レポートで少しでも関心をおもちいただけましたら、ぜひお気軽にご相談ください。